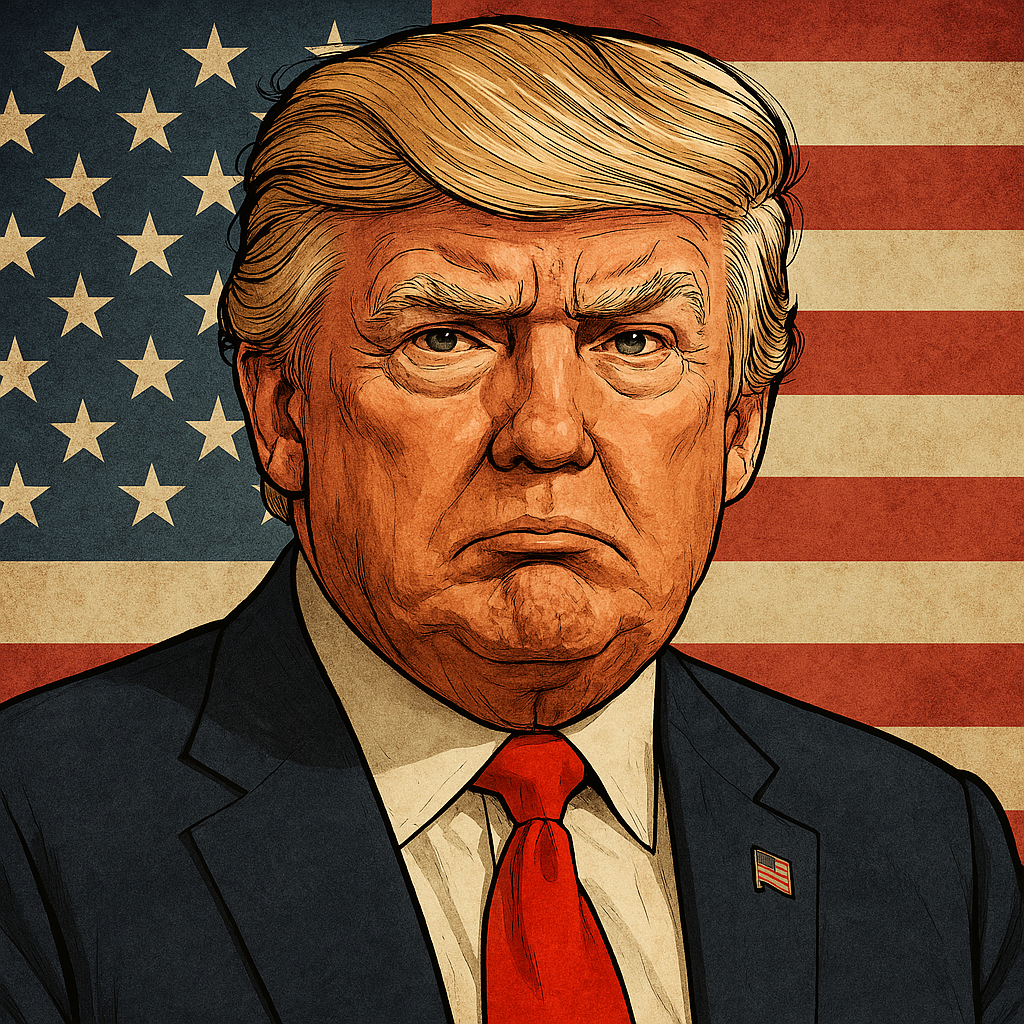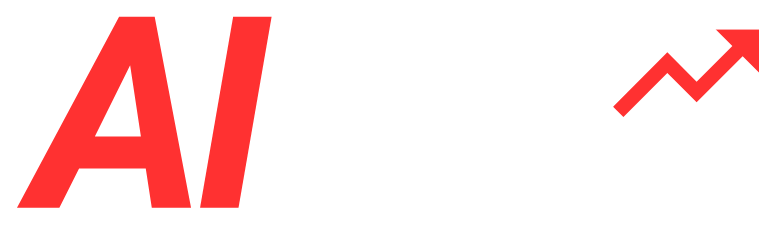2025年4月、トランプ大統領が発表した関税政策が、世界の経済や技術分野に大きな衝撃を与えました。
とりわけ、今後の生成AIの価格や供給体制に与える影響は深刻です。
本記事では、具体的な事例や企業動向をもとに、その影響の全貌を探ってまいります。
米国の関税措置とその背景
トランプ大統領は「解放の日」として、全輸入品に対して一律10%の関税を導入し、加えて中国からの輸入品には34%の追加関税を課すと発表しました。
これにより、中国製品への関税率は既存の20%と合わせて合計54%に達します。
日本製品には24%、EU製品には20%の関税が設定され、台湾および韓国製品にも高率な関税が課されるとされていますが、台湾製品への具体的な関税率は現時点では明らかになっておりません。
この措置の名目は「国家安全保障と競争力強化」ですが、実態としては、AI・半導体・量子技術といった戦略的先端分野における覇権争いの一環であると見られております。
各国に対する米国の関税一覧(2025年4月時点、判明分)
| 輸入元 | 関税率 | 主な影響品目 |
|---|---|---|
| 全世界 | +10% | 全輸入製品 |
| 中国 | +54% | 電子機器、部品全般 |
| 台湾 | 不明 | GPU(NVIDIA製)など? |
| 日本 | +24% | 自動車、精密機器など |
| EU(欧州連合) | +20% | 工業製品、農産物など |
| 韓国 | +25% | 半導体、ディスプレイ等 |
GPU価格の高騰とAI産業への影響
NVIDIAと中国の関係概要(2025年時点)
| 項目 | 内容 |
| 中国でのNVIDIA製GPU需要 | ByteDance、Tencent、AlibabaなどがH20チップを中心に大量購入しております |
| 規制対象となるチップ | H100、A100など最先端チップは米国からの輸出が禁止されております |
| 規制回避チップ | H20(性能を制限した中国向けモデル) |
| 合計契約額(2025年) | 約160億ドル以上(H20などを中心に注文) |
| 課題 | 米国の規制強化により調達継続が不透明となっております |
| 関税影響 | 米国からの輸入チップに最大54%の関税が課され、中国企業側も価格転嫁の懸念があります |
| 代替策 | 一部企業は国外でGPUレンタルや非正規ルート調達も検討しております |
生成AIモデルの学習や推論に用いられるGPUは、NVIDIAが圧倒的シェアを誇っております。
H100やA100、H20といった高性能モデルは台湾のTSMCで製造されておりますが、台湾製品への関税率は明確に報道されておらず、実際に関税が適用されるかどうかは不透明です。
実際、生成AI開発に関わる米国企業(OpenAI、Anthropic、Cohereなど)は、クラウド基盤維持費やモデル運用コストの増加を見込んでおり、SaaS形式で提供されているAPI料金への転嫁が進む見通しです。
ChatGPT Plusなどの月額制サービスの値上げや、法人向けAPIの従量課金単価の見直しも示唆されております。
中国・欧州・日本の反応と報復措置
中国政府は直後に、米国製品全体に対して34%の関税を課す報復措置を発表しました。
EUも対抗措置を検討しており、世界的な貿易摩擦の再燃が懸念されております。
日本では石破首相が、今回の関税措置に対して「極めて遺憾」との声明を発表し、影響を緩和するための支援策として、国内企業への資金支援や雇用保護策の検討を進めております。
自動車産業や電子部品業界を中心に、米国市場での価格競争力の低下が懸念されております。
なお、台湾は報復措置を取らず、米国との関係維持を優先する姿勢を示しており、台湾の総統はゼロ関税を基盤とする米国との貿易交渉を提案し、米国からの輸入拡大による貿易不均衡の是正を目指す意向を表明しております。
AIスタートアップと中小企業ユーザーへの波及
関税の影響は大手企業にとどまりません。
GPUをクラウドで借用しているAIスタートアップや、生成AIを活用している中小企業にとって、インフラコストの上昇は死活問題になり得ます。
特に、LLM(大規模言語モデル)をAPI経由で活用している事業者は、利用量に応じた従量課金に直面することになります。
想定される影響の具体例
- 生成AI導入・運用コストの上昇
- サービス価格(チャットボット、AI記事作成、画像生成等)の値上げ
- 中小企業における生成AI利用の縮小や敬遠
国産AIと脱アメリカ依存の動き
生成AIの国別活用状況について、以下のようにアメリカと日本の比較を表にまとめました。
生成AIの活用に関する日米比較(2025年調査、複数民間調査の平均値に基づく推定)
| 指標 | 日本 | アメリカ |
| 個人の生成AI利用率 | 約9.1% | 約46.3% |
| 企業の生成AI導入率 | 約60.0% | 約25.9% |
| 導入済企業のうち業務で利用している割合 | 約46.8% | 約84.7% |
| 積極的に活用する方針を持つ企業の割合 | 約15.7% | 約71.2% |
この表は参考データであり、今後の正式な統計調査の発表により数値が変更される可能性があります。
この表からも分かるとおり、アメリカでは個人・企業のいずれもが生成AIの導入と活用において積極的ですが、最新のデータでは日本企業の導入率も大きく伸びております。
特に生成AIを業務に取り入れる企業が増加傾向にあることから、今後の動向が注目されます。
こうした状況下、日本国内では国産AIの開発や、日本語特化型の中小モデル(例:ELYZA、rinna、Abejaなど)への注目が集まっております。
政府も2025年度中に、生成AIの計算資源確保に向けた国家戦略をまとめる方針を示しており、国産GPU開発や省電力AIモデルの研究が強化される見通しです。
また、一部企業ではChatGPT APIの利用から、ローカル処理型モデル(LLaMA、Mistral、Japanese StableLMなど)への移行も進んでおります。
これは価格上昇リスクを回避し、機密性とデータ主権を確保するための動きとして注目されております。
まとめ:AI時代における“経済安全保障”
今回の関税措置は、生成AIという先端技術にも深く影響を及ぼす“経済安全保障”の問題であるといえます。
今後は、単なるテクノロジー活用ではなく、地政学的リスクや国際経済の構造的変化を見据えた技術選定と利用戦略が求められます。
ユーザーや企業の皆さまには、生成AIの“価格の裏側”にあるグローバルな動向に敏感であることが求められます。
そして、日本全体としても、自立的なAI開発体制の確立と、外部依存リスクの低減に向けた挑戦が求められております。