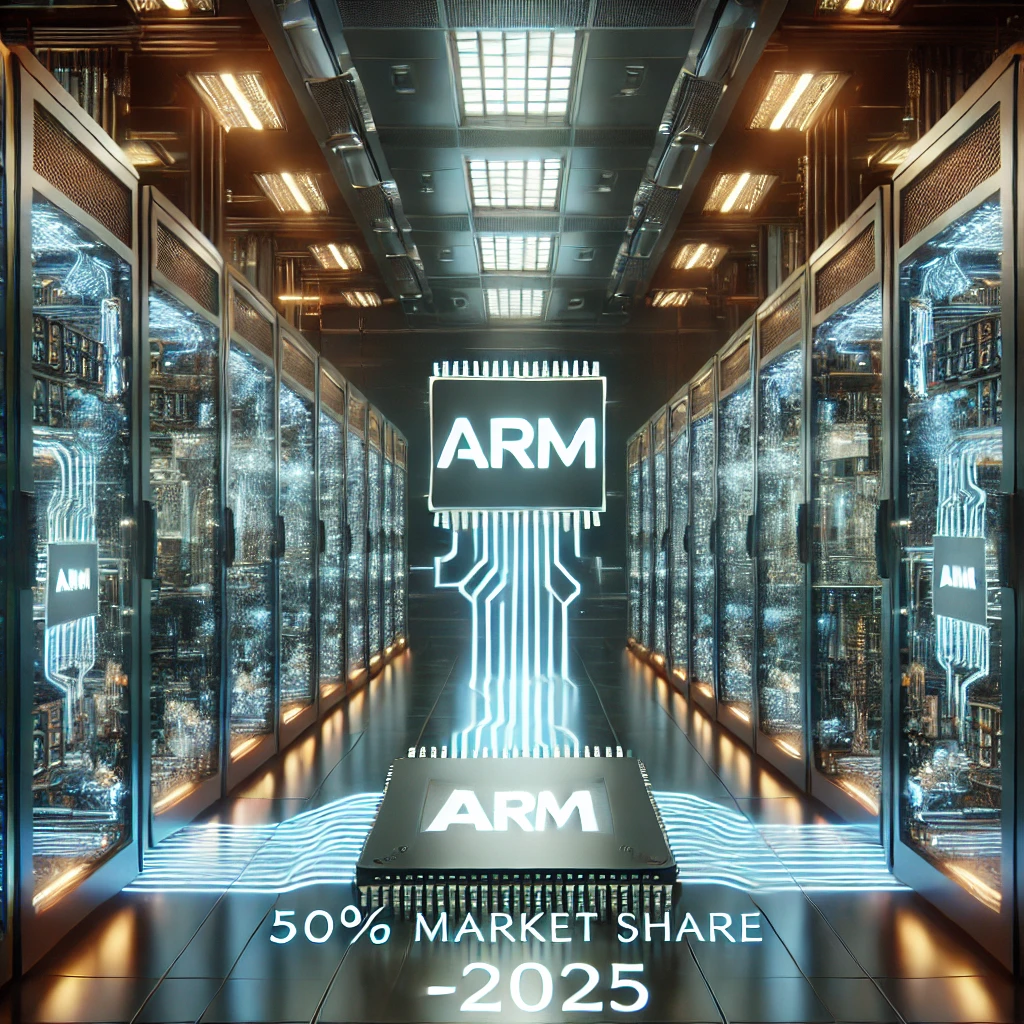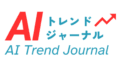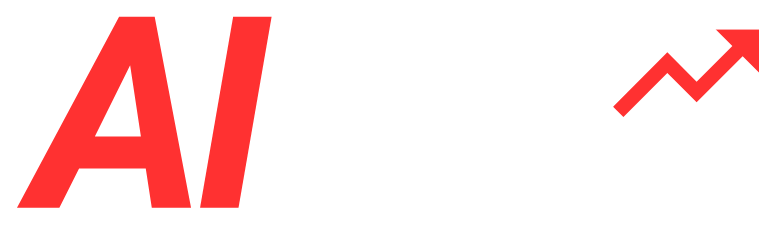AI需要が追い風、ArmベースCPUの急拡大
ソフトバンクグループ傘下の英半導体設計会社Arm(アーム)の技術を用いたデータセンター向けCPUが、2025年末までに市場シェアを約50%に伸ばす見通しとなった。
現在の約15%から3倍以上の拡大となる見込みで、生成AIの普及を背景に、電力効率の良さが評価されている。
Armのインフラ部門責任者モハメド・アワド氏がロイターに明かした。
ホストチップとしての役割と低消費電力の強み
Arm設計のCPUは、AIシステムにおいて「ホストチップ」として使われる。
これは、GPUなどの演算チップに指示を出す中枢的役割を担うもので、例えばNVIDIAの最先端AIシステムには「Grace(グレース)」と呼ばれるArmベースのチップが搭載されている。
Arm製品の最大の強みは、x86系CPU(インテル、AMD)に比べて圧倒的に消費電力が低い点だ。
クラウドデータセンターでは、電力消費の削減が運営コストに直結するため、この点が高く評価されている。
大手テック企業の採用状況
Amazonは独自設計のArmベースCPUを導入しており、ここ2年間で追加したデータセンター容量の50%以上をArm技術に依存している。
また、Google(アルファベット)やMicrosoftも独自のArmベースチップの開発を進めており、x86一強体制に風穴を開けている。
ソフトウェア対応の進展が鍵
かつてArmは、ソフトウェアの互換性や開発環境の未整備により、サーバー市場での展開に苦戦していた。
しかし近年は「Armファースト」でソフトウェアが設計されるようになっており、クラウドベンダー側も積極的に対応を進めているという。
アワド氏は「Armが中心に設計される時代に入った」と語っている。
補足情報:Armアーキテクチャの歴史と特徴
Armの起源は1983年、イギリスのAcorn Computers社にさかのぼる。
そこで「Acorn RISC Machine(ARM)」という省電力で高性能なCPUを目指すプロジェクトがスタート。
1990年にはAppleとVLSI Technologyの支援を受けて独立し、「Advanced RISC Machines」として再出発した。
ArmのアーキテクチャはRISC(Reduced Instruction Set Computer)設計を基盤にしており、少ない命令セットで効率的な処理を実現している。
これによりモバイル機器やIoT、そして近年ではAI向けデータセンターでも広く採用されるようになった。
インテルやAMDとの競争も激化
Armの躍進に対し、インテルやAMDもAI対応を強化。
インテルは最新のXeonチップで少コアでも高いパフォーマンスを実現し、TCO削減を狙っている。
2025年はデータセンター用CPU市場において、技術革新とシェア争いが激しさを増す年になりそうだ。