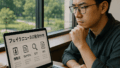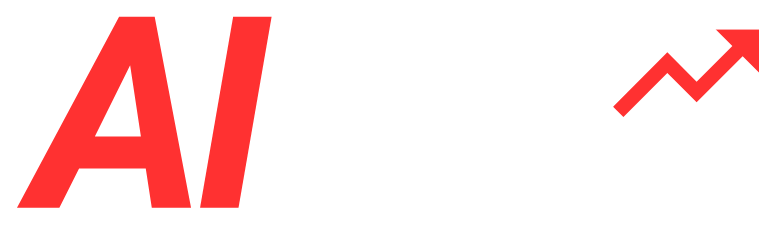AI導入で不正検知が精緻化、摘発リスクが過去最高に
ドイツ連邦金融監督庁(BaFin)は、金融市場における不正行為の監視体制を一段と強化している。2025年6月2日、マーク・ブランソン長官は、人工知能(AI)技術を市場監視システムに導入したことで、違反行為の摘発可能性が「これまでになく高まっている」と述べた。
AIは取引データを自動解析し、疑わしいパターンを従来より高精度で検出可能とされており、当局による迅速な対応を可能にしている。
ワイヤーカード事件の反省から、監督体制強化へ
BaFinは、2020年に発覚した大規模な不正会計事件――決済サービス企業ワイヤーカードの破綻――を契機に、監督能力の欠如を問われ厳しい批判を受けた。
この事件では、約19億ユーロに相当する資産が「存在しない」ことが発覚し、同社は破綻。監督当局の対応が不十分だったことが国内外から非難を集めた。
その反省から、ブランソン長官の就任以降、BaFinは監督機能の再構築に着手。AIの導入はその一環であり、組織の信頼回復に向けた象徴的な施策と位置付けられている。
監視技術の最前線:RegTechとSupTechとは
今回のAI導入は、いわゆる「RegTech(レグテック)」および「SupTech(サプテック)」と呼ばれる新技術群の一部として注目されている。
RegTechとは、金融機関が規制に適応するための技術であり、コンプライアンスの自動化や効率化を図る。SupTechは、監督当局がデータ分析やリスク評価をAIなどの技術で強化する手法を指す。
これにより、取引の異常値をリアルタイムで監視し、早期警告を発することが可能になりつつある。
AI導入に伴う課題:倫理と法的責任の線引き
AI導入は監視体制を飛躍的に強化するが、一方で倫理的・法的な課題も浮上している。
AIによる判断プロセスの「説明可能性(Explainability)」、個人情報の保護、差別的バイアスの排除などが重要な論点だ。
これらの課題に対応すべく、欧州連合(EU)では「AI規則(AI Act)」の導入が進められており、金融分野においてもAI利用の透明性と適正性を確保する枠組みづくりが進行中である。
まとめ:AI活用で金融監督の未来像が変わる
BaFinのAI活用は、技術による公共ガバナンスの強化を象徴する事例だ。
過去の不祥事から学び、再発防止と透明性の向上を図る姿勢は、今後他国の金融監督にも影響を与える可能性がある。
金融市場の健全性を維持するため、技術と倫理のバランスをいかに取っていくかが、今後の大きな課題となる。