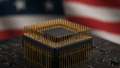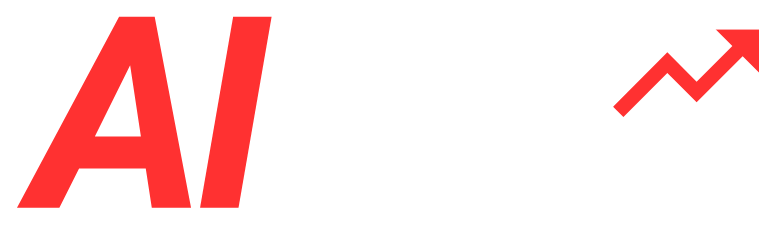中国の検索大手バイドゥは、同社の自動運転タクシーサービス「Apollo Go(アポロ・ゴー)」の欧州展開を視野に、スイスおよびトルコでの試験運用を準備していることが明らかになった。
スイス・ポスト傘下の公共交通企業と連携し、同国での商用化を目指す。
これにより、中国国内ですでに普及が進むロボタクシーのグローバル展開が一歩前進する形となる。
スイスとトルコでの試験運用、欧州初の取り組み
2025年5月14日、米紙ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)は、バイドゥがスイス・ポストの子会社「ポストオート」との協議を進めており、スイス国内で自社の自動運転タクシーサービス「Apollo Go」を開始する計画だと報じた。
また、トルコでも同様のサービス展開が検討されており、これはバイドゥにとって中国国外での初の商用展開となる。
Apollo Goはすでに中国国内では数百万人に利用されているが、欧州の複雑な交通ルールや規制環境の中での試験運用は、同社にとって重要なステップとなる。
バイドゥの自動運転事業の歩みと現在
バイドゥは2013年から自動運転開発に着手し、2017年にはオープンプラットフォーム「Apollo」を発表。
以降、2020年に北京市での試験運用を皮切りに、「Apollo Go」は中国の武漢、重慶、深センなどで展開を拡大した。
2022年8月には、武漢と重慶で完全無人運転(レベル4)の商用ロボタクシー運行が認可された。
2024年第2四半期までに累計890,000件のオーダーを達成し、2024年末までには武漢に1,000台の完全無人車両を配備予定である。
世界のロボタクシー情勢とバイドゥの狙い
現在、無人タクシー市場では米国のWaymo(Google)やCruise(GM傘下)が先行。
Waymoは2018年からアリゾナ州で商用運行を開始し、現在はサンフランシスコやロサンゼルス、アトランタなど5都市に展開。
また、日本市場でのマップ作成にも着手しており、グローバル展開を視野に入れている。
対するバイドゥは、中国での圧倒的シェアを背景に、技術と実績を欧州に輸出することで、国際競争に本格参入しようとしている。
技術面・法規制面での課題と対応
欧州での展開には、各国の交通法、プライバシー規制、安全基準といった法制度への適応が必須となる。
バイドゥはこの点について、現地企業との提携や、地域ごとのインフラに適応するカスタマイズを進めているとみられる。
また、AIによる走行判断、センサー技術の安全性確保、異なる道路環境への即応なども技術面での重要課題である。
補足情報:ロボタクシーの歴史と進化
ロボタクシーの研究は2000年代から各国で進められており、技術の転換点となったのは2010年代初頭のGoogleによる自動運転実証実験。
その後、米国ではWaymoが2018年に初の完全商用運行を開始、中国ではバイドゥが政府支援のもと自動運転都市を整備してきた。
日本でもホンダが2026年を目処に東京・お台場でGM、Cruiseと共同で無人タクシー運行を予定しており、グローバルな商用化競争が激化している。
今後の展望
バイドゥは「Apollo Go」の欧州進出により、世界市場での地位向上を目指す。
2025年以降は、中東やアジア諸国への展開も検討しており、AIモビリティのグローバル標準を担う企業としての地歩を固めようとしている。